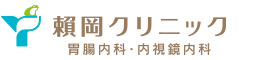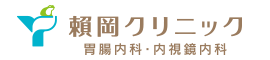⚠️感染性胃腸炎について⚠️
2019年01月28日
梅のつぼみがほころぶ季節となりました。皆様、いかがお過ごしですか?
年末年始より感染性胃腸炎の方が多く来院されています。
感染性胃腸炎とは細菌やウイルスによる感染症の総称で、毎年秋~冬にかけて多く流行します。
原因はノロウイルス、ロタウイルスなどのウイルスの他、細菌や寄生虫などが挙げられます。
今回は冬場に多く見られるノロウイルスについてご紹介いたします。
ノロウイルスとは?
冬季の食中毒の原因の80%以上を占めており、感染性胃腸炎の集団発生や嘔吐下痢症からも多くノロウイルスが検出されています。
ノロウイルスはとても小さい(インフルエンザウイルスの1/3程度)のですが、感染力が非常に強く、
患者さんの便1gには100万個~10億個、嘔吐物1gには2.5~100万個と、大量のウイルスがいます。
(10から100個程度あれば感染すると言われています)
タオル等に付着すると冬場では約3週間生きており、手に付いたら1回程度の手洗いでは落ちません。
感染経路は?
- カキ等の2枚貝を生で食べたとき
- ノロウイルスの付着した食物や、感染者が調理した食品を食べたとき
- ノロウイルスが手に付着し、その手が口に触れたとき
- ノロウイルスが飛沫・粉塵として舞い上がり、口や鼻から入ったとき などが挙げられます。
カキ(などの二枚貝)のノロウイルス汚染
感染者から便等に大量に排出されたウイルスは、家庭から下水処理場をへて河川や海に流れ込みます。
プランクトンを餌とするカキは1時間に18リットルもの海水を取り込むため、カキの肝臓にウイルスが付着・蓄積し、それを人が食べて感染します。
カキ以外の二枚貝(アサリ、シジミなど)もノロウイルスに汚染されますが、これらを生で食べることはあまりないので食べて感染するケースはほどんどありません。
症状は?
12~24時間の潜伏期間ののち発症します。
吐き気、おう吐、発熱、腹痛などの症状が現れ、多くの場合は2~3日で治まります。
かかってしまったら?
ノロウイルスに効く薬は今のところありません。吐き気や脱水症状などへの対処療法のみとなります。
小さなお子様やご高齢の方、基礎体力の弱い方は、おう吐や下痢などにより脱水症状を起こすことがありますので早めの受診をおすすめします。
食事は消化の良い物(おかゆ、ポタージュスープ、うどん等)を摂り、水分補給にも注意しましょう。
避けた方が良いものは、脂肪や糖分、食物線維の多い物、香辛料や海藻、乾物などです。
人から人へ感染するため、患者さんがトイレの後などに手を洗うのはもちろんですが、家族や周りの人も手洗いやうがいをしっかり行い、患者さんとのタオルの共有は避ける、患者さんの入浴は最後にするなど周囲への感染に注意しましょう。
また、患者さんが触れた物(ドアノブや蛇口、調理器具や食器など)は次亜塩素酸ナトリウム0.02%で、直接汚物の付いた床や衣服は0.1%で消毒すると良いでしょう。
!次亜塩素酸ナトリウム消毒液の作り方!
0.02%…市販の塩素系漂白剤を250倍に薄める。
0.1%… 〃 50倍に薄める。
症状が治まれば会社や学校へ行くことは可能ですが、便からのウイルスの排出が2~3週間ほど続くことがあり、二次感染を防ぐためにも十分な手洗いが大切です。
予防方法は?
- 基本は手洗い!
トイレの後や調理・食事の前には十分なうがい・手洗いを行いましょう。
2009年の新型インフルエンザ大流行の際、その年の感染性胃腸炎は減少しています。
これは新型インフルエンザの予防目的で手洗い・うがいを励行したことも、減少の理由の一つと考えられています。
- 汚物処理に注意!
便やおう吐物を処理する時には、使い捨て手袋、マスク、エプロンなどを着用しましょう。
汚物で汚れたものは次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。
- 食品はしっかり加熱!
カキなどの二枚貝を調理する場合には、中心部まで十分に加熱しましょう。
(中心部の温度が75℃で1分以上の加熱が目安です)
ノロウイルスは感染力が強く集団発生を起こしやすいため、注意が必要です。予防を徹底しましょう。